「読めるけど書くのが苦手」
こういう子、わりとたくさんいますよね。
すらすら読めるのになぁ。。どうしてかしら??
背景には、見る力(視覚機能)と動かす力(運動・協調機能)のアンバランスが隠れていることが少なくありません。
本日はその疑問を解説したいと思います。
1. 【視覚機能】の観点から見る「読めるけど書けない」
●読むことに必要な視機能
読む時には主に以下の機能が使われます:
- 固視(こし):目をしっかりと止めて対象に焦点を合わせる力
- 追従眼球運動:行をたどるときに滑らかに目を動かす力
- 視覚認知:文字の形や構造を正しく捉えて理解する力
これらが十分であれば「読む」ことは可能なのです。
では、一方で、「書く」作業には、何が必要でしょう?
●書くときにはさらに求められる力
- 視空間認知:文字の形や位置、大きさのイメージを空間的に把握する力
- 視覚記憶:見た文字を脳内に一時的に保持し、それを再現する力
- 視運動協応(ビジュアルモーターインテグレーション):見たものを手で再現する力(手眼協応)
この「視運動協応」に課題があると、見えているものを手で再現するのが苦手になります。これが、「読めるのに書けない」の大きな要因のひとつです。
さあ、ちょっと難しい言葉も出てきましたね💦
『視運動協応』あまり聞いたことないですよね。
視知覚の検査を受けたことのある方は、「VMIテスト」とか、やりませんでしたか?
これがまさに視運動協応のテストですね。
視運動協応(Visual Motor Integration:VMI)
先生によっては「視覚と運動の統合」とか「視覚ー運動統合能力」などと表現されるかたもいらっしゃると思います。
✅ 視運動協応(Visual Motor Integration:VMI)
- 定義:視覚で捉えた情報をもとに、手や身体を適切に動かす力
- 例:見た形をなぞる・模写する、見た位置に手を伸ばす、字を書くときに形を再現する など
- 特徴:視覚と運動の「協調性」に焦点を当てた概念です。
さあ、「書く」という作業は、当然手を動かさなければなりません。なので、身体機能も大きく影響します。
2. 【身体機能】との関係
●姿勢や体幹の安定
書くときには、姿勢の安定も非常に重要です。体幹が不安定だったり、椅子にしっかり座れていなかったりすると、手先の動きにも影響が出ます。
●指先の巧緻性
鉛筆操作がぎこちない場合、思った形を表現できず「苦手意識」につながりやすくなります。
✋なぜ「身体感覚」がカギになるのか?
書字は「見る」「動かす」の連携作業。
しかし、書くための姿勢保持・手指の微調整・空間の認識などは、
視覚以外の感覚(固有感覚や前庭覚)によって支えられています。
つまり、
📌目は見えているけど、身体の“感じ方”や“動かし方”がうまくいかないと、書字がうまくいかない
ということが起こります。
3. 【認知的負荷】の問題
書くことには多くの工程が含まれます:
- 文字を「思い出す」
- 「どう書くか」を計画する
- 形やバランスを考えながら再現する
この一連の流れに高い認知負荷がかかり、注意が分散してしまう子もいます。
その結果、「読む」はできても、「書く」が難しくなるのです。
4. 【支援の方向性】
●視運動協応を高めるトレーニング
- 迷路・なぞり・図形模写などで「見て動かす」力を養う
- ストリングス遊び(あやとりのような)やお箸トレーニングも有効
●視空間認知を鍛える
- 積み木やパズル、左右反転・回転図形の理解など空間把握を遊びの中で強化
●筆記量の工夫
文字数を減らす、ひらがなや漢字をあらかじめ印刷しておくなど、「考えて書く」負担を軽減
5. 【見逃されがちなポイント】
「書くのが苦手」という訴えの背景には、「見えにくさ」や「感覚のズレ」があることが非常に多いです。
単に練習させるのではなく、「どの段階でつまずいているのか」を丁寧に観察し、段階的に支援することが鍵です。
まとめ
「読めるのに書けない」には理由があります。
それは「意欲」や「性格」の問題ではなく、発達過程で育ちにくかった視覚・身体・認知の機能が影響している可能性が高いのです。
だからこそ、
子どもの「困りごと」を「できていないこと」ではなく、「何がうまくできないのか」に分解して見ていくこと。
そして、その子の「できた!」を少しずつ積み上げていく支援が大切ですね。
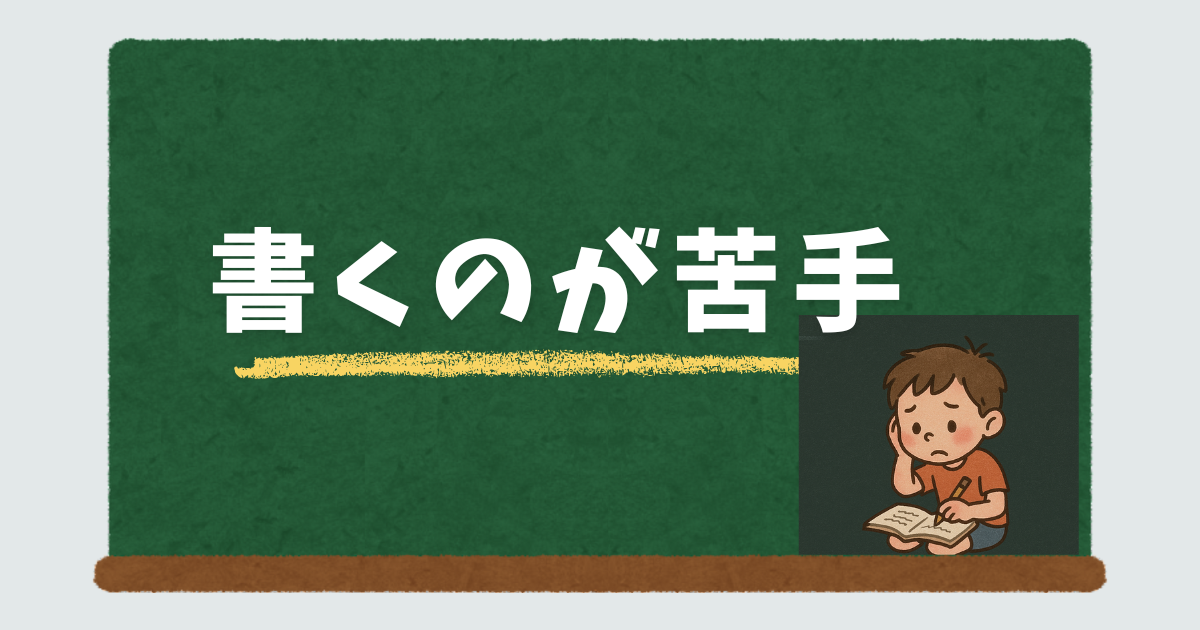
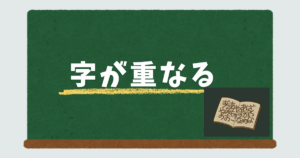
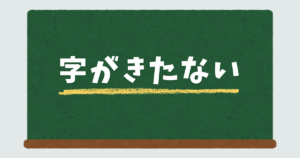
コメント